1 『人物』の写真・動画への写り込みの法律問題
ブログや動画製作において写真や動画を撮影した際、意図せず或いはどうしても排除することができずに、『人物』が写り込んでしまうことがあります。
ブロガー、動画クリエイターの方々においても、「大丈夫なのかなあ?」などと気になっていることも多いと思います。また、事実上何も請求されていないからいいやと検討をやめてしまっていることもあるのではないでしょうか?
今回はその『人物』の写真・動画への写り込みの法律問題について解説します。
SNS・ブログ・動画投稿サイトへの使用のための撮影において人物が写り込んでしまうことはしばしばあるでしょう。
このような場合に、当該人物への許諾などを取得せずにそのまま写真や動画を公開してしまうと、〇写り込みの人物へのフォーカスの度合い、〇写真・動画全体に対する割合、〇人物の特定可能性などの判断要素から、肖像権侵害と認定される可能性が出てきます。
究極的には肖像権侵害・不法行為への該当性については個別具体的事情により訴訟により判断されることになりますが、仮に最終的な訴訟の結果として侵害に該当しないとされたとしても、被撮影者からの事実上のクレームへの対応など様々な問題も発生し得るでしょう。
2 肖像権との関係
肖像権とは、プライバシーの権利の一種として 、個人の私生活上の自由として、みだりに自己の容貌や姿態を撮影されたり、撮影された肖像写真を公表されないという人格的利益とされています。
最高裁判例においても
「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。」(最大判昭和44年12月24日刑集23巻12号1625頁〔京都府学連事件〕)
「人は,みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁参照)。」(最一小判平成17年11月10日民集59巻9号2428頁)
とされています。
肖像権侵害の判断基準としては、裁判例等から、〇人物の写り込みの大小、〇容貌の特定の程度、〇公開を望むか否かに関するその他事情等が検討の対象となると考えられます。
事例として、核燃料サイクル施設の事業者らの発行する地域情報誌の表紙において、ある人物が漁をしている写真を無断で撮影及び掲載したという裁判例(青森地判平成7年3月28日判タ891号213頁)では、
「原告がゴリ漁をしているところを撮影したものであって風景写真と言えなくもないが、原告がかなり大きく写っており、横顔とはいえ原告をよく知っている者が見れば被写体が原告であることが容易に判断できるものと認められる。したがってこのような写真の無断撮影、掲載は原告の肖像権を侵害するものと認めるのが相当」
として、肖像権侵害に基づく損害賠償請求を認めています。
3 パブリシティ権との関係
写りこんだ人物が著名人である場合などにはパブリシティ権との問題も発生し得ます。
パブリシティ権とは、人の肖像等が有する顧客吸引力の排他的な利用権とされています。
パブリシティ権の侵害が成立する要件としては、
「肖像等を無断で使用する行為は,①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し,③肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となると解するのが相当」(最一小判平成24年2月2日民集66巻2号89頁)
とされています。
【肖像権とパブリシティ権はどう違う?】
肖像に関連する権利という意味では共通となりますが、肖像権は人格的利益を中心に考える権利であり、パブリシティ権は顧客吸引力という財産的利益を中心に考える権利である点で差異があるといえるでしょう。
4 実際の対応はどうする?
著作権における軽微な写り込みの規定※などはないことから、ちょっとした写り込みだから大丈夫などということはありません。
肖像権との関係では特定性を消去するための処理や撮影及び公開の許諾(なお注意点として、撮影を許諾したとしても、たとえば、動画投稿サイトなどWEBサイトでの公開や使用までの許諾は別物と考えられるため、「撮影」と「公開や使用方法」の許諾は別物として考え、実際の使用形態を説明した許諾の取得が必要となると考えられます)を得てからの使用などの対応が求められることとなります。
※著作権と軽微な写り込みについては下記関連記事をご参照。

関連書籍:『Q&Aデジタルマーケティングの法律実務~押さえておくべき先端分野の留意点とリスク対策~』(拙著、2021年刊、日本加除出版)
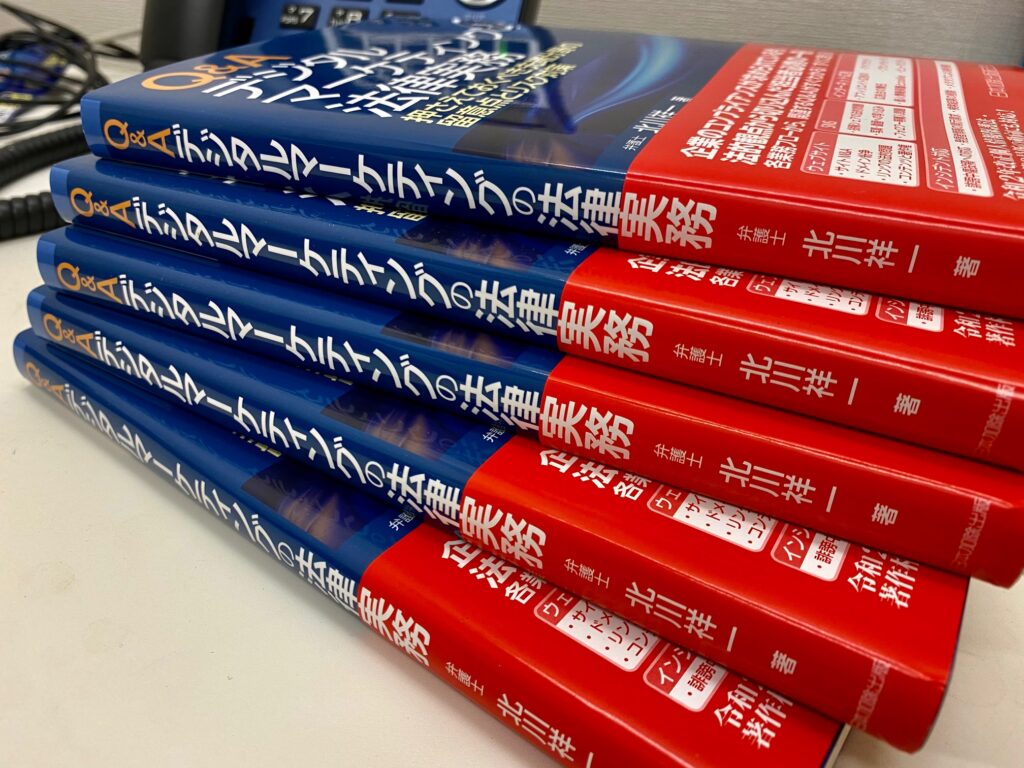
※本稿は、私見が含まれ、また、実際の取引・具体的案件などに対する助言を目的とするものではありません。実際の取引・具体的案件の実行などに際しては、必ず個別具体的事情を基に専門家への相談などを行う必要がある点にはご注意ください。





コメント